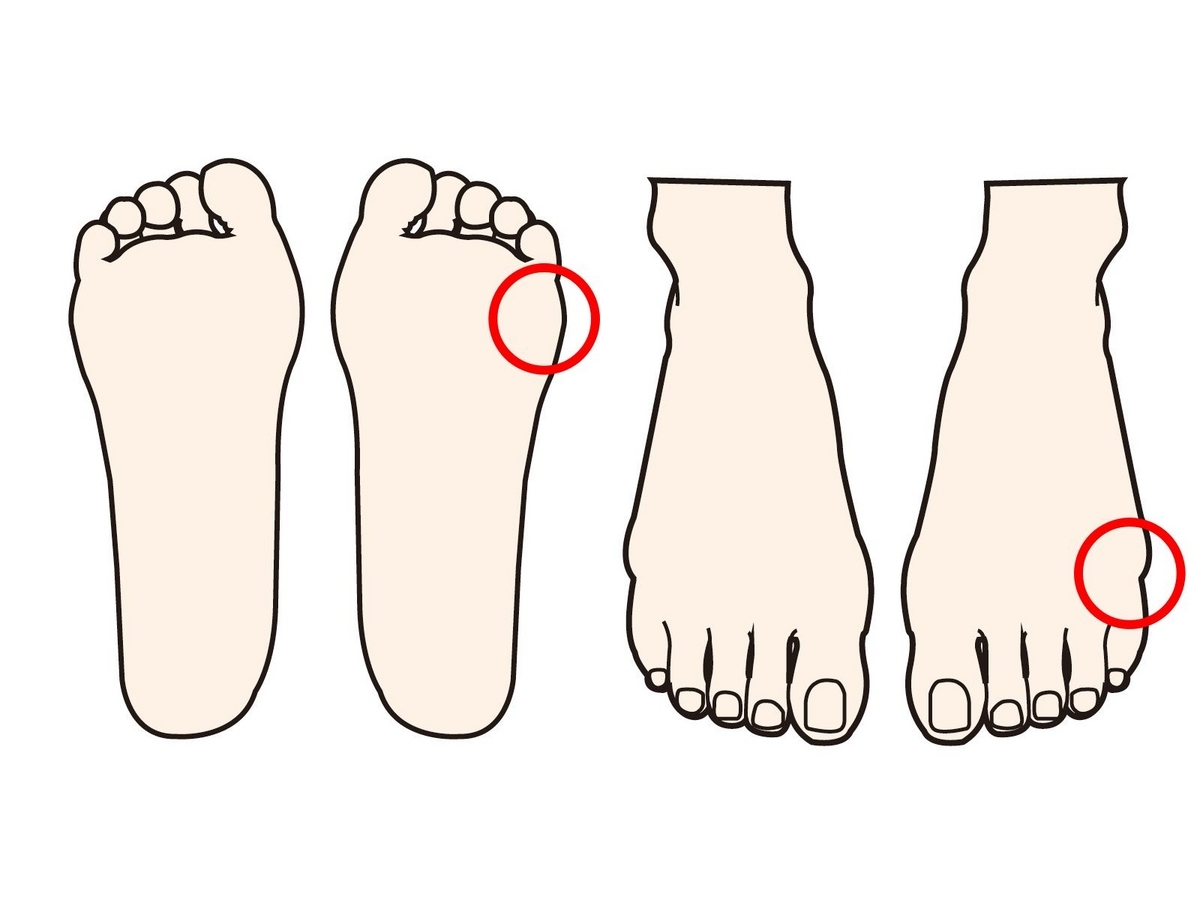皆さんこんにちは。
気付けば8月も終盤、北アルプス等の3000m峰では早くも秋の足音が聞こえるようになってきました。
私は登山を始めて丁度1年程になるのですが、この1年間雪山を含めてトータル60日間程活動してきました。
単純計算で月に5日程度、山に入ってることになります。
登山を始めた当初は往復7kmの工程でもヒーコラ言っていた私ですが、最近では日帰りで往復20km程度を歩くという山行も増えてきており、自分自身の成長も感じています。
そこで、この1年を飾る集大成として、果たして日帰りで槍ヶ岳に登れるのか挑戦してみました!
北アルプス界隈ではその形容からランドマーク的かつ、登山者の憧れ的な存在のあの槍ヶ岳です。
私もいつかは槍ヶ岳。。。
なんて最初の頃は思ってましたし遠巻きから眺めるだけの存在だったのですが、まさかこんなに早く挑戦する日が来るとは思ってもみませんでした。
結論からいうと、槍ヶ岳は日帰り登山可能です。
ただし夏季限定です。冬季で日帰りはまず無理でしょう。
今回は、実際の工程や日帰りで槍ヶ岳に登るコツやポイントについて、実体験を踏まえながら解説していこうと思います。

ご参考までに、YAMAPの活動日記のリンクを張り付けておきます。
アクセス方法
まず槍ヶ岳へのアクセス方法についてです。
槍ヶ岳はその位置関係上、裏銀座コースや表銀座コース、パノラマ銀座コース、TJARでも通過する西鎌尾根、登山者なら誰しも憧れるといっても過言ではない槍・穂高縦走路。
これら各種北アルプス縦走路でほぼ必ず経過する中継地点になります。
そのため登山口も各コースに応じて他種ある訳ですが、日帰りとなると最短距離となる新穂高温泉からが最有力候補です。
往復路で約30kmいかないくらいの距離になります。
実際私も今回の日帰りでは新穂高を利用させていただきました。
登山口周辺、駐車場
新穂高温泉は各山(槍ヶ岳、西穂高、双六岳・笠ヶ岳等)の玄関口として知られる一方、その利便性の高さとは裏腹に駐車場の数が限られています。
リンクが今季の駐車場地図です。
無料Pは第5、第8、第10のみで、ハイシーズンの土日や連休前後だと登山口に最も近い第5Pはとにかく混み合います。
第5Pで車中泊する場合は遅くとも前日の夕方には到着しておくと良いでしょう。トイレは仮設トイレが駐車場の入り口付近に設置されてました。
水洗でキレイでした。トイレットペーパーも備え付けられています。
有料でも良いなら更に登山口に近い第3Pや、深山山荘の駐車場を予約して利用すると良いでしょう。
登山道、登山口~槍ヶ岳山荘
登山口から飛騨沢の区間の前半線において、特に危険な箇所はありません。
途中渡渉があったりますが、橋が掛けられてますので安心して歩けます。小屋締め以降は橋は取り外されるみたいなので、渡渉が必要になります。

個人的には白出沢から滝谷区間、湿ってツルツル滑る石がゴロゴロ転がってる箇所が苦手です。千丈沢までは緩やかな登りが続きますが、そこまで来ると視界が開けて槍ヶ岳の山頂が見えるようになります。
ここから後半戦の始まりです。

千丈沢から槍ヶ岳山荘まではこの急勾配のカールを登ることになり、この区間で大半の時間を要します。山頂が見えてから約600mの上がりますので、山頂は見えてるのになかなか稜線に上がれない、、、
というもどかしい時間が続き、ここが一番の踏ん張りどころです。頑張りましょう。
でもふと後ろを振り返ると、笠ヶ岳や氷河が削ったカールといった壮観が拝めます。


また夏なら足元に咲き誇る高山植物が疲れを癒してくれることでしょう。

途中、千丈沢分岐にぶつかり、千丈沢乗越と飛騨乗越のルートが選択できます。
天気が良ければ千丈沢乗越が良いかもしれません。
今回はガスで眺望が期待薄だったので、往路復路とも飛騨乗越でいきました。
槍ヶ岳山荘~槍ヶ岳頂上
テント場が見えたら槍ヶ岳山荘は直ぐです。
槍ヶ岳山荘から山頂までは片道約30分の岩登りになります。足場は安定してますし、鎖や杭が打ち込まれてますので、見た目ほど難しくありません。

ゆっくり慎重に行動しましょう。万が一ここで滑落・落下すれば軽度の怪我では済まない可能性が高いです。
また人が多い場合は、向かって左側の梯子が登り、右側が下りの梯子です。
山頂は10名くらいしか滞在できない狭いエリアになりますので、混雑回避するように行動しましょう。

なお、この区間はヘルメット着用を推奨します。
これは自身の滑落・落下からだけでなく、落石から身を守る意味もあります。
ザックは山荘前にデポし、必要最低限の荷物で空身で登ると良いです。
復路
同じ道を辿って下山します。
工事用の林道歩きが往復で約13kmを占めるため、とにかくこれが長いです。
心折れないように最初からそのつもりで意気込んでいきましょう。
逆にメリットは涼しいです。
日帰り登山のポイント
とにかく装備を必要最低限、軽くするのがポイント、いうことに今回気付きました。
1日で長く距離を歩くには兎にも角にも装備の軽さが最重要になります。
重量の中で一番重いのは水になる訳ですが、途中、槍平山荘で購入可能ですし、無料で水も利用できます。
それから先、千丈沢の前に最終水場もありますし、槍ヶ岳山荘でも飲料水は購入可能です。
実際私は2.5L持って担ぎましたが、途中で補給すれば良かったなあと思ったので、改めてここに記載します。
でも結局足りなくて、帰りの際に槍平山荘で自販機でポカリ500mlを購入しました(確か500円)。
今回1日で30km程度のロングコースは自身としても初挑戦。
自分の成長を感じると共に、長く歩けることで山行の幅も広がるという新しい領域に入った気がします。
次は1dayで表銀座やパノラマ銀座にトライしたいと思ってるところです。
この山行記録がどなたかの役に立てれば幸いです。
それではご安全に!

ブログのランキングに参加してます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓